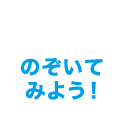休憩タイム
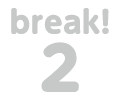
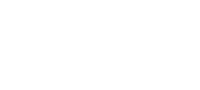
情 報
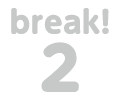
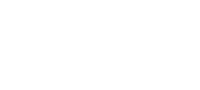
へ〜!なるほど!そうだったんだ!
ガラスびんをより知ってもらえる情報です
その6 【水平リサイクル】ってなんだ?
ガラスびんのリサイクルを例に挙げると、空きびんから作った再生原料「カレット」を利用して再びガラスびんを作るリサイクルのことです(びんtoびん)。
言い換えれば、リサイクルの元になったものとリサイクルでつくられたものの機能・物性が変わらないリサイクルを水平リサイクルといいます。
これに対して、カレットをガラスびん以外の原料として使用するリサイクル、例えば道路の舗装材に使用することをカスケードリサイクルといいます。カスケードとは階段状に連続した小さな滝のことを言い、先に進むにつれて(品質が)どんどん下がっていく(=同じものに戻らない)ことに掛けた用語です。
ガラスびんはライフサイクルの短い容器ですので、びんからびんへの(びんtoびん)リサイクルは、リサイクルの回転が速く、資源を節約して何度でも原料として利用することのできる効率の良いリサイクル方法といえます。
その5
【リターナブルびん】の
イイところ
ガラスびんは容器のなかで唯一くり返し洗って再使用できる容器です。再使用できるびん(リターナブルびん)には、一升びんやビールびん、牛乳びんなどがあります。またびんの肩部や裾部に「R」のマークが入っているRマークびんは、日本ガラスびん協会が認定したリターナブルびんです。
リユースではガラスびんの「生産時のCO2排出」が最初の1回で済むため、とても環境に優しいのです。ビールの500mlリターナブルびんの例では20回再使用するのと、1回使って捨ててしまう(リサイクルせずに埋め立てる)のを比べると、CO2排出量は77%も少なくなります。
そんなリターナブルびんも寿命が来れば廃棄されますが、カレットになってリサイクルされ、新しいびんに生まれ変わります。
その4 つるつるじゃない!
たいていのガラスびんの底にはデコボコした模様が一周して入っていますが、これはナーリングと呼びます。金属の円柱にギザギザをつけた加工を、英語でナーリング加工といい、滑り止めの役割をするのですが、ガラスびんでは底のナーリングに傷がついても、デコボコの山に傷がつくだけで、ガラスびん全体が割れないようにしています。
このナーリングはびんの胴や肩の部分にも加工されることがあり、こちらは日本語で梨地と呼ばれていますが、これも単なる装飾ではなく底のナーリングと同様にびん同士の衝突による傷を梨地部分で止める役割があります。
ちなみに、肩部に梨地加工がある633ml共通リターナブルビールびんでは、9700個ほどのデコボコがびんの金型に加工されています。その加工の後にさらに「BEER」の文字を彫るので、デコボコはもうちょっと少なくなります。
その3 【ガラスびんの体の名前】
ガラスびんはその場所によって呼び分けるように名前がついています。上から順に、口、首、肩、胴、裾、底(尻とも)という具合です。普通のびんには手はありませんが、大きなびんにハンドルが付いたものは把手と呼ばれる手がある場合もあります。目鼻耳足はない…と思います。
口の一番上の平滑な部分は天面とも言われます。王冠で栓をするびんなどでは口の上の部分をリップ(唇)とも呼びます。ただしその下の少し膨れた部分はほっぺではなく、鏑と呼びます。鏑矢という飛ばすと音がする矢の鏑という部分に形が似ているからです。他に珍しいものではびんの裾の部分に小さなへこみがあるものもあります。彫刻や模様のあるびんを回して一定の向きにそろえるためのへこみで、センタリングスポットもしくはディンプル(えくぼ)といいます。ウイスキーびんなどで見られます。
体の場所の呼び名ではないですが、口の部分にはスカートと呼ばれる場所もあります。いろいろな形のびんで確かめてみましょう。
その2 【ガラスびんの名札】
びんの底や裾にはいろいろな情報が刻印されています。びんを生産した会社・工場が分かる記号、生産した金型の番号数字、製品によっては生産した時期が分かる記号などです。この記号はそれぞれのびん会社、製品のルールでびん1本1本に付けられていて、それを調べることでびんの品質保証に役立てられます。
金型の番号は数字の他に、バーコードやドットコードと呼ばれるものが刻印されている場合もあります。検査機が、ある規則に従ってこれを番号に読み替えて他の品質情報と紐づけられます。
日本ガラスびん協会のホームページには生産会社・工場の記号の一覧が載っています。これを見ればガラスびんがどこでつくられたのかが分かります。
https://glassbottle.org/about/factory/
注:この他にもいくつかのびん会社の識別記号があります。
その1
【びんビール】の
王冠栓のひだはいくつ?
ビールびんの王冠栓のひだ(スカートといいます)の数は21個です。このひだの数は世界共通です。
円形は力学的に3の倍数で支えると安定するのですが、18個では締めつけが弱くてすぐに外れてしまい、24個では強すぎて開けにくいため、21個が定着しました。
金属の王冠栓が普及したのは、ガラスびん製造の機械化により、びんを同じ寸法で安定してつくれるようになったからです。びんの高さや口部の形状のばらつきが少なくなり、王冠栓がしやすくなったのです。それ以前はびんの寸法が多少不ぞろいでも栓ができるコルクの栓が多く使われていました。