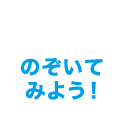びんのイイ話
長い歴史のなかで
ガラスびんは役立っています


ガラスびんが誕生したのは、びっくりするほど昔のことです。
4000年も前のエジプトで、砂を熱で溶かしてできたのが最初と言われています。
日本人のくらしのなかに登場し始めたのが明治時代で、当時はとても貴重でした。
それほど長い歴史をもつガラスびんには、魅力がぎっしり詰まっています
ガラスびんの知識
昔から使われているびんの
イイところは

- びんの中身はいろいろ
透き通って見えるから安心 - ジャム、ジュース、調味料、クスリなど、いろんなものを入れて保存できるガラスびん。透明だから、中に何が入っている一目でわかって、安心です。

- いろんな形、いろんな色
個性ゆたかなびんがいっぱい - 角ばったびん、丸みのあるびん、くぼみのあるびん、模様が刻み込まれたびん、緑びん・茶びん・青びんなど、個性ゆたかなびんがいっぱいあります。

- おいしく感じるのは
びんの持つ不思議な力 - 味もニオイもないガラスびんは、中身のおいしさが変わらない。やさしい手ざわりや口あたり、見た目の美しさ、そそぐ時のトクトクという音まで、おいしさを引き立てます。

- 天然素材でつくられるから、
人にも地球にもやさしい - ガラスびんの主な原料は、けい砂・石灰石・ソーダ灰と、空きびんをくだいたカレットです。人体に悪い影響をおよぼす素材は含んでいません。


ガラスびんの製造工程
安心して使えるびんは
品質管理されて生産しています
-
 調合
調合
カレットと、ミキサーで均一な状態にした、けい砂・石灰石・ソーダ灰などの天然素材を混ぜ合わせます。

-
 溶解
溶解
耐火レンガでつくられた大きな窯の中に原料を入れて、約1500°Cの熱でドロドロに溶かします。

-
 ゴブ
ゴブ
カット
溶かしたガラスから、びんをつくるのに必要な量だけ切り取ります。そのかたまりをゴブといいます。

-
 成形
成形
ゴブを金型に入れて、ガラスびんの形にします。いつ・どの金型でつくられたのか、びんの底にマークがつきます。

-
 徐冷
徐冷
熱を持っているガラスびんを、割れないように少しづつゆっくり冷やしていきます。

-
 検査
検査
ガラスびんの形や細かいキズまで、検査機や人の目できびしくチェックします。

-
 加工
加工
検査が終わったガラスびんに、印刷をしたり、ラベルをはったり、塗装する場合もあります。

-
 出荷
出荷
検査や加工が終わったびんは、出荷先に合わせた形態で梱包されて、中身を詰める工場へ運ばれます。


ガラスの知識
くらしで活躍する
ガラスの仲間たち
身近にある種類
- ソーダ石灰ガラス


- クリスタルガラス


- 耐熱ガラス


- 成分も溶ける温度も異なるため、
リサイクルするときには別々に! - これらのガラスは、見た目には似ていますが、成分も溶ける温度も異なります。ガラスびんと同じ組成の食器も、砕けるとクリスタルガラス製と区別がつかないため、しっかり分別しましょう!