自治体の取り組み事例
中部東海エリア
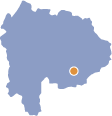
山梨県 富士吉田市
富士吉田市の概要(平成31年1月1日現在)
- ●人口: 富士吉田市49,134人
- ●世帯数: 富士吉田市19,851世帯
- ●面積:富士吉田市121,740㎢
- ●ステーション数:1,356カ所
- ●分別基準適合物引渡量:
無色144,226㎏、
茶色149,491㎏、
その他の色72,784㎏
〔エリア特集〕住民の理解と協力、自治体の工夫で効率的なリサイクルループを構築…①
自治体の学ぶ意欲と住民の高い意識こそが、
高い品質を支えている。

平成15年4月より、富士吉田市では、富士吉田市環境美化センターの稼働と並行して、それまで不燃物扱いだったガラスびんのコンテナによる資源物収集を始めました。循環型社会を目指す観点から、開始にあたっては先進自治体の視察を行い、参考にしました。当初は周知不足もあり、住民の皆さんがびんをどのコンテナに仕分けするのか混乱しましたが、自治会単位での回覧板による周知など地道な広報活動により、いまでは徹底した周知と収集がなされています。それは、コンテナの数や置き場など設置方法や分別方法から資源化センターでの選別方法に至るまで、自分たちの町にあったベストな方法を模索してきた資源物収集の成果です。 ステーションの設置は、使う住民の単独設置や自治会による設置などさまざまです。基本的に住民のみなさんにルールを守る意識が高く、ステーションの掃除など、しっかりと管理されています。 コンテナの収集時にはびんはとても清潔に保たれており、その場でリターナブルびんとワンウェイびんに分別。さらに資源化センターでは、丁寧に色別の手選別を行なっており、分別基準適合物引渡量が7.46kg/人(全国平均5.32kg)と、全国でも優秀な結果に。また、その他の色の構成比も20%弱と、全国平均の28%と比べても優秀であり、選別精度の高さを表わしています。これらの品質は、まさに住民の協力と選別作業時の熟練の技のおかげ。 富士吉田市が高品質を生み出す要因は、自治体としての確かな計画性や実践方法の工夫と住民への周知、加えて住民の地道な協力活動と手選別作業の腕が支えていると言えます。

お話を伺った
富士吉田市 市民生活部
環境美化センター
舟久保さん(左)
武藤さん(右)

- 分別区分
- 混合収集
ガラスびんとガラス、せとものを混合収集。市がルールを周知しているので、びんはよく洗われており、中身もほとんど残っていない
- 収集容器
- コンテナ
指定袋での収集は可燃ごみのみ。びん、缶、不燃物は指定の色別のコンテナに。収集は民間委託
- 収集場所
- ステーション
住民の単独設置や自治会で設置。当番制で町内の住民が掃除ほか維持管理を行っている
-

 ステーション(集積所)
ステーション(集積所) -

 びんの他、缶や不燃物もそれぞれ
びんの他、缶や不燃物もそれぞれ
コンテナが用意され、
同時回収 -

 市内5カ所に、びん以外の資源ごみを
市内5カ所に、びん以外の資源ごみを
回収する
ステーションを設置
- 収集車両
- 平ボディ
収集車7台、びんの収集は2トン車4台、資源物回収は2台の計13台で稼働。びんの収集は、1台につき2人で行っている
-

 びんの収集は平ボディ車4台で対応
びんの収集は平ボディ車4台で対応
-

 順次到着するトラックから
順次到着するトラックから
丁寧に降ろし
速やかに選別作業へ -

 センターにコンテナの保管場所を設け
センターにコンテナの保管場所を設け
収集日に合わせてステーションへ設置
- 選別手段
- 手選別
コンベアなどの設備などは使用せずに作業員の丁寧かつ正確な手作業で選別を行っており、高い選別精度を誇っている
-

 選別時は作業員それぞれが
選別時は作業員それぞれが
種類ごとのカゴを用意して選別 -

 びんの色分け、キャップ、異物除去など
びんの色分け、キャップ、異物除去など
短時間で正確に行われている -

 リターナブルびんも仕分けされる
リターナブルびんも仕分けされる
- 保管設備
- ストックヤード
センター室内に設置されており、雨風の影響もなく
屋外とはシャッターで仕切られている
-

 色別に仕切られたヤード
色別に仕切られたヤード
-

 手選別後、保管された無色びん
手選別後、保管された無色びん
品質向上のためのポイント
- ●富士五湖エリアのケーブルテレビのデータ放送で、ごみの出し方や収集曜日の情報などを広報。また市の防災アプリにも、暮らしの情報として掲載している。
- ●市で収集カレンダーを作成して、市民に配布している。カレンダーのビジュアルは、富士吉田らしく富士山の写真で、市内外で人気を博している。
- ●外国人住民のために、英語版の区報をホームページに掲載し、周知を行っている。
- アプリで情報を掲載

- パンフレットなどで資源ごみの出し方やマップを告知

【お詫びと訂正】
富士吉田市の概要については、すでに発行済の「びんの3R通信vol.49」に掲載されている内容から一部変更しております。
このページに掲載されている内容が最終の情報となりますことをご了承ください。





